だれもが楽しめるものづくりのテーマパークを目指す越前鯖江地域は、7つの地場産業が集まる「つくるまち」。
この地域で開催されるオープンファクトリーイベント、RENEWに参加し、ものづくりの現場と働く人たちを取材しました。
産業を観光につなげることで、職人も、住民も、訪れる人も、みんながしあわせになって伝統が続いていく。
そんな仕組みが、動き始めています。
「越前鯖江を、ものづくりのテーマパークにしたいんです」
夢を語ってくれたのは、鯖江市の眼鏡材料商社KISSOの社長、吉川精一さん。
KISSOさんは、眼鏡の素材である「セルロースアセテート」という色鮮やかな樹脂を使い、宝石のようなアクセサリーを制作、販売しています。
フェリシモでは、el:mentとのコラボで、イヤカフリングとルーペネックレスを作りました。
また、以前のGO!PEACE!の記事では、鯖江と眼鏡の歴史とKISSOさんの描く未来についてご紹介しました。
「眼鏡のまちから生まれるアクセサリー⁉︎ 鯖江の過去と現在、未来について」


KISSOさんは、越前鯖江地域の産業観光を推進する、一般社団法人SOE(以下:SOE)の副理事でもあります。
「産業観光を通じて、持続可能な地域をつくる」ことを目指すSOEですが、そもそも、越前鯖江地域とは、どのような場所なのでしょうか?
「つくるまち」越前鯖江
三方を山に囲まれ、福井県のほぼ中央に位置する越前鯖江地域は、ものづくりの名産地。
越前漆器、越前和紙、越前打刃物、越前箪笥、越前焼といった伝統工芸に加えて、眼鏡・繊維を合わせた7つの地場産業が、半径10km圏内に集まっています。
これほど密集してさまざまな工房が立ち並ぶ地域は、全国でも数えるほどしかありません。




このままではいけない。自分たちで売る力をつけなければ。
越前鯖江地域にあるものづくりの会社のほとんどは、企業から注文を受けて作るいわゆる下請けの会社。
メーカーからの「この企画で、何個納品してください」という注文に対して、正確に作って納品することが大切な仕事でした。
しかし機械での大量生産が可能になるにつれ、注文が減り廃業する企業も出てきました。
「このままではいけない、自分たちで商品を売る力をつけなければ」と地域の企業が集まり、2015年に初めてのRENEWを開催しました。
当初は、鯖江の地場産業である漆器、眼鏡の工房をオープンファクトリーにすることからスタート。ものづくりの過程や職人の思いを直接「見て、聞いて」もらうことで、ファンになってくれる人が徐々に増えていきました。
2017年より地域を拡大し、和紙、打ち刃物、箪笥、焼き物、眼鏡、繊維の工房が加わり、7つの産業を体験できる、今のRENEWの形になりました。

見学やワークショップを通じて、作り手の想いや背景を知り、技術を体験しながら商品の購入を楽しめる。
その魅力が人を呼び、RENEWのイベント規模は大きくなっていきます。
企業が雇用をすることで定住してもらいたいという気持ちや、1年に1回のイベントではなく、通年楽しめる産業観光の街にしたいというビジョンの元、2022年にSOEが立ち上がりました。
現在では、参加企業が事務所や工房を改装したり、ショップを開いたりすることで、通年楽しめるまさに「ものづくりのテーマパーク」のような街になってきています。

工場見学ツアーに参加して
刃物の工場は、金属のすこしツンとする臭いで、漆器の工場は、漆のすこし酸っぱいような臭い。
ものづくりの現場に行ってこその感覚は、驚くことばかりでした。
2024年11月に開催されたRENEWに参加して、いくつかの工房や工場を見学した様子をご紹介します。

工場見学ツアーに参加したのは、越前漆器の製造・販売を行う「漆琳堂(しつりんどう)」。
寛政5年(1793年)の創業以来、器に漆を塗る「塗師」として、越前漆器づくりを営み続けています。


ツアーでは、漆器ができるまでの工程を学ぶことができます。
まずは、木材を削って器の形を作っていきます。紙型にあわせてすべて同じ角度の器を作れるのが職人技です。


職人は道具をつくるところからが仕事。
漆を塗るヘラは、職人自ら小刀で薄く削り、形を整えます。

そして肝心の漆。器に入れてラップをかけ保存しています。
定番色の黒はもちろん、白や水色など、カラフルな漆もありました。

お椀の外面に漆を塗る過程では、お椀を轆轤(ろくろ)に当て、刷毛を使って塗っていきます。
その後、湿度が一定に保たれる倉庫の中にセットし、回しながら乾燥させます。


ツアーの最後に、漆琳堂で働き始めて6年目の髙橋菜摘さんにお話を伺いました。

ー漆琳堂でのお仕事はどうですか?
髙橋さん:私は大学で漆芸について学んでいたのですが、そのときは半年間かけて、大きなオブジェなどを作っていたんです。なので一日に同じものをたくさん作るのは、漆琳堂に入ってからが初めてで、働き始めてから学びました。同じ姿勢をとり続けなきゃいけなかったり、大変なこともありますが、毎日楽しいですね。ひとつひとつ商品を作っていく今の仕事は、好きなことだなと思っています。
ー今後の目標や夢はありますか?
髙橋さん:漆琳堂では、私のような若いスタッフも多く、自分たちで考えて仕事ができることも多いです。自分たちで考えた企画で、漆器の商品を開発して作っていくのが夢です。
見学のなかで感じたのは、ふだん生活の中で使う「もの」が作られている過程を、私はまったく知らないということでした。
ひとつのものをつくるにも、受け継がれてきた技術があり、多くの人が関わり、いくつもの工程があります。
伝統工芸である越前漆器の起源は、およそ1500年前にさかのぼるそう。
よりよいものをつくるために歩んできた長い歴史と人々に、思いを馳せました。
GO!PEACE!な商品をつくる過程
次に工場見学に伺ったのは、眼鏡の生産と販売をおこなう眼鏡工房の「プラスジャック」。
ここでは、今回のKISSOさんとel:mentのコラボ商品も、一部生産されています。


越前鯖江地方の産業は、ほとんどが分業制をとっています。
眼鏡であれば、素材を仕入れる商社、生産する工房、また、レンズを取り扱う会社も異なっていて、すべてが合わさって眼鏡という商品になります。
今回のイヤカフリングとルーペネックレスも、生産の一部はKISSOさんとは別の会社である、プラスジャックさんに担っていただいたのです。
工場見学を案内いただいた日は、商品の磨きの工程を見ることができました。
バレルと呼ばれる機械の中に、いろんな素材のチップをパーツと一緒に入れ、機械を回すことで、チップがパーツにぶつかり、パーツが磨かれていきます。
この作業をチップの素材を変えて何度も行うことで、パーツの輝き具合が増します。

バレルでの磨きが終わったら、最後はひとつひとつ、手磨きでていねいに表面を磨いていきます。
ちょうどルーペのパーツの磨きを見ることができました。
磨く前にもすでに輝いているように見えたパーツですが、回転する円盤に角度を変えながら当てて磨くとさらに輝きが増します。


バレルでの磨きから手磨きへ。磨きの工程だけでも、7~10日間ほどはかかるとのこと。
いくつもの工程を経てお手元に届く商品は、いちばん輝いて素材の美しさが引き出された状態です。
ぜひお手に取ってみてくださいね。
訪れる人も、職人も元気になる地域へ
工場見学を終えたあとは、SOEのメンバーである西山ほゆさんにお話しを伺いました。

ー近年の越前鯖江地方に変化は感じますか?
西山さん:私は2016年に鯖江に移り住んだのですが、当時と比べて店舗がものすごく増えたなと感じます。基本的にBtoBでメーカーなどに商品の販売をする会社がほとんどだったのが、自社商品を開発してお店を構えて、一般のお客さまに対して売っていく。BtoCへの流れを感じています。
地域が変わることで、ビジネス関係の方だけではなく、一般のお客さまがお店に行ってみたいという理由で、一年通して地域に来てくださっています。
ー西山さんご自身の変化は何かありますか?
西山さん:鯖江に来る前は特にやりたいことがなかったんですよね。それが、RENEWを通して職人さんとかかわるうちに、やりたいことが見つかったんです。私のやりたいことは、職人さんのものづくりへの思いを世の中に伝えていくこと。
今は本当にこの地域が大好きで、どうしたら伝えられるんだろう?といつも考えています。
ーそう思ったきっかけとなる、職人さんとのエピソードはありますか?
西山さん:RENEWに関わって1年目のとき、初めてお会いした焼き物の職人さんが「僕はしゃべるのが得意じゃないんだ」とおっしゃっていたんです。けれど焼き物作りのことを話し始めたら2時間半ぐらいお話してくださったんですよ。情熱がすごくて。毎日思いを持ってやられていることだから、きっと気づいたときには時間がたっていたんでしょうね。
そのとき、職人さんたちはこんなに思いをもってお仕事をされてるんだと心を打たれました。
こんなに語れることがあるのに、世に知られていない職人さんたちが地域には大勢いるんだと。RENEWやSOEの活動を通して職人さんたちの思いを伝えていくのが私の仕事だと思うと、背筋が伸びますね。
西山さんのようなスタッフの思いがさらなる思いをよび、当日ボランティアとして参加する若者も増えています。
大学の授業をきっかけに興味を持ち参加した方や、地元を元気にしたいという夢をかなえるため越前鯖江の事例を学びたいと参加した方も働かれていました。
それぞれが自分の大切な思いをもって、RENEWに集まっています。

「産業観光」で世界の見方が変わるかも?
今回の取材でRENEWに参加して職人さんや携わる方々のお話を伺い、「つくる」とはどういうことなのか、改めて考えました。
「ものづくり」の背景にある、語りきれない魅力。
産地を訪れてその一部に触れることで、日々の暮らしで考えることが、変わってきたのです。
たとえば食事のとき、器は食事を彩るものであり、深く考えることはありませんでした。
しかし、器にやどる作り手の技術や思いに触れたことで、見方が変わります。
「どこで、どんな人がつくった器なのかな。」
「いつから使われているものなんだろう。」
つくられた背景を思うという新しい見方が、暮らしを深め、彩り、楽しいものにしていくのだと感じました。
越前鯖江地域を観光する前としたあとでは、見える景色が変わるのではないでしょうか?
















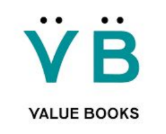













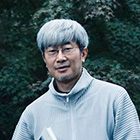












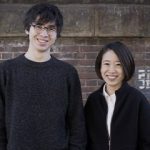










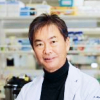










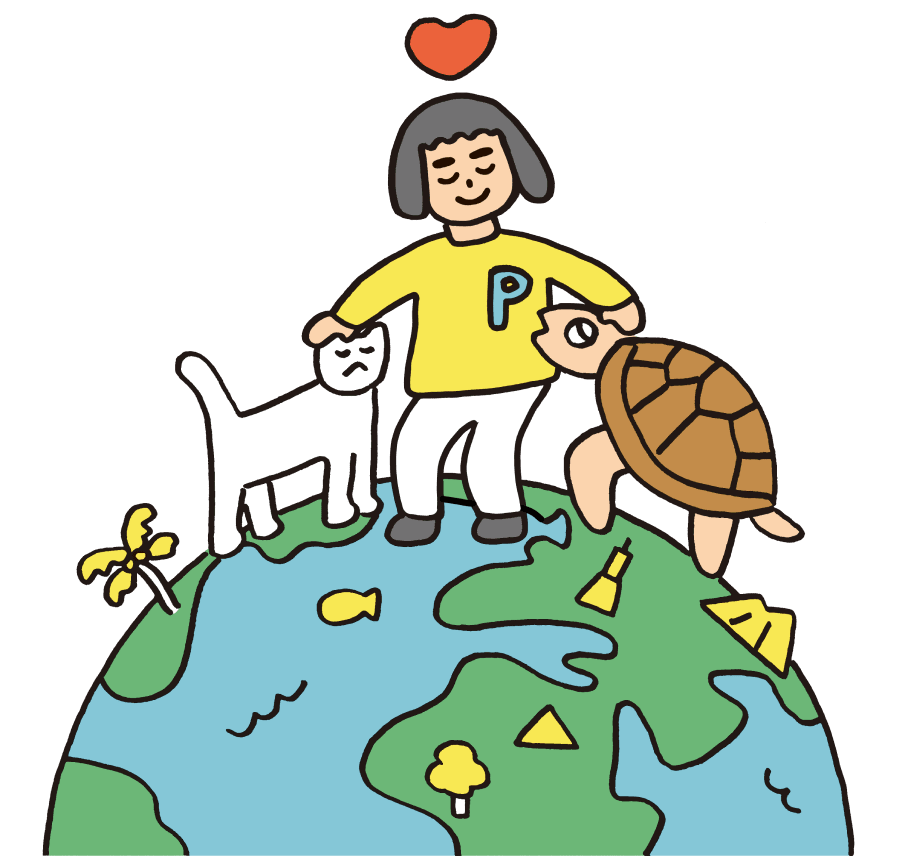
応援コメント ✍🏻️
コメント数 2 件